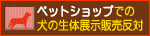小林信美の英国情報(24)愛犬の生と死:3.死と向き合う
(24)愛犬の生と死:3.死と向き合う
マチルダが亡くなったのは、春の訪れを告げる水仙のつぼみがふくらみ始めた2月の半ば過ぎだった。悪性の肝臓腫瘍だというのに、最後まで彼女の病状が回復することを信じて疑わなかった私は、心の準備など全くできていなかった。あまりのショックに何もする気が起きなかったが、彼女にふさわしい、きちんとしたお葬式をしてあげたいという思いから、亡くなった翌朝すぐにインターネットでペット用葬儀場を探すことにした。ここで考慮に入れなければならなかったのは、マチルダの遺骨(灰)を手元に置いておきたいということだった。これは、自分が亡くなったらマチルダのお骨と一緒に埋葬してもらいたいと思っているためで、彼女のお骨をそれまでとっておく必要があったからだ(注1)。そういうわけで、ペットの遺体を個別に火葬するサービスのあるペット用の火葬場を探すことにしたのだが、実は、これは思ったほど一般的ではないことがわかった。動物愛護の国として知られるこの英国でも、驚いたことに、ペットを数匹単位で火葬するのは普通のことで、また遺骨が他の廃棄物と共に消却、破棄されるケースもかなり多いといわれている。
そういうわけで、ペットの尊厳を尊重し、ペットを一匹ずつ火葬してくれる、その名も「Dignity(尊厳)(注2)」という葬儀場を選んだ。Dignityは、上記のような問題をかかえるペット葬儀業界の現状を憂慮したバリー・スタージェンさんと、その妻のキャロラインさんが、1992年にロンドンから車で南西に2時間ほどの所にあるオーディアム(Odiham)という村に設立した会社だ。

夫妻は、生前大切にされていたペットに相応しい、きめこまやかなサービスを提供しようと、1988年に住居として購入した古いレンガ工場の跡地にあったビクトリア時代に造られた焼き釜(上記写真参照)を火葬場に改造し、この事業を始めた。現在は夫妻の長男のケビン・スタージェン氏が両親の遺志を継ぎ経営に携わっている。また、ケビン氏は、業界を代表するペット葬儀場・ペット墓地協会(Association of Private Pet Cemeteries and Crematoria) の会長としても活躍している。
運良く空きがあり、マチルダの葬儀はその日の午後に行われることになった。電話では霊柩車のサービスもあり、直接葬儀場まで出向かなくてもよいと説明されたが、始めから最後の最後までマチルダと過ごしたいと思っており、彼女を自分で葬儀場に「送って行く」つもりでいたので断った。
電話を切ると、すぐにマチルダの遺体をシーツにくるみ、前夜まで使っていたベッドに再び寝かせ、車に乗せた。彼女が亡くなってからまだ一日も経っておらず、この時点では、これがマチルダとの最後の車の旅となるのであるという実感は、まだなかった。しかし、途中、いつものようにサービスステーションで彼女の好みそうなマフィンを買い車に戻り、そういえば、これを一緒に食べる相手はもういないのだなと思うと、マチルダなしの生活の味気なさを垣間みたような気がして、突然、悲しさが津波のようにどっと押し寄せて来た。しかし、葬儀場まで車で1時間近くあり、めそめそはしていられない。車のエンジンをかけると、そそくさとサービスステーションを後にした。
オーディアムは、イギリスにある典型的な村で、かつてマチルダと訪れた数々の村を思い起こさせ、彼女とまた旅行に出かけているような妄想にかられるのだった。葬儀場に着くと、人懐っこそうな女性が「お別れの部屋」に案内してくれ、マチルダと最後のひとときを過ごす時間が与えられた。部屋はどこかのB&Bの一部屋を思い起こさせるような内装だったが、ベッドに横たわる剥製化したマチルダをまじまじと見ていたら、やはり彼女はもうこの世のものではないことがひしひしと感じられるのだった。それと同時に、もう彼女の病気のことを心配しなくてもよい。また、会社に行くためにひとりぼっちにしなくてもよいのだと思うと、やや気持ちが楽になるような気もした。そうこうしているうちに、さきほどの女性が現れ、遺髪と「遺爪」さらに足形をとってくれるというので、お願いした。
そしていよいよ最後の時がやってきた。葬儀場の庭園の真ん中にある火葬場に連れて行かれると、かけていた毛布など遺体以外の物が一切が取りのぞかれ、マチルダの硬直した遺体だけがぽつんと冷たい鉄板の上にのせられた。時は2月。陽は出ていたものの、まだまだ寒さは厳しく、ふと寒くないだろうかという考えが頭をよぎった。もちろん、そんなことはないのだが、もう二度と会うことはできないマチルダに何かしてあげたいという気持ちにかられた。すると、硬直して尾が反り上がったために露出された肛門のまわりの汚れに気がついた。かわいそうなマチルダ!思わず持っていたちり紙で、丁寧に拭きとってあげた。すると今までがまんしていた涙が噴水のように一気に流れ出し、止まらなくなった。
「よろしいですか?」
担当の男性が火葬炉の横からそそくさと出て来て、マチルダを火葬炉へ入れるというしぐさをした。私は言葉が全く出ず、力なくうなずくのが精一杯だった。そして、ごうごうと音を立てて勢いよく燃えている火葬炉の中に、マチルダの遺体を乗せた鉄板が静かに挿し入れられ、戸がパタンと閉められた。
火葬が終わるまで数時間かかるということで、葬儀場から車で10分くらいの村で待つことにした。古いレンガ建ての家並みの続くこの小さな村を歩いていると、マチルダと出かけた国内旅行のことが次から次へと思いおこされた。離婚し、フルタイムで働くようになったが、相変わらず博士課程の論文の執筆に追われ、気持ちの余裕がなかった私は、亡くなる前の4年ほどマチルダを旅行に連れて行ってあげることもできなかった。彼女と出会ってから、私が仕事に出るようになるまで、私たちはほぼ一日24時間一緒にいることが多かったから、もしかしたら、私が仕事で一日中家を開けているのが辛すぎたのでは、と思うと激しい罪悪感にかられ、またそれに涙するのであった。
葬儀場に戻ると、マチルダは小さな金属性の骨壺に入れられて出て来た。またさきほどの案内の女性が現れ、遺髪、遺爪と足形にセットを渡してくれ、私をなぐさめようとしてか、自分の愛犬の死について話してくれた。そして「今は、つらいかも知れないけれど、時がいやしてくれるわ」というのが彼女の別れ際のことばだった。
最初から最後までほぼ一貫した良心的なサービスであったが、もちろんこれもビジネスである。費用は「一般」の葬儀サービスに比べればやや割高ではあった。しかし、人の弱みにつけ込んでというようなイヤらしい押しつけ的サービスはなく、私にとっては、マチルダとの最後のお別れのためにできる限りのことをしてあげることができた、という満足した気持ちで葬儀場を後にすることができた。
さて、マチルダが亡くなってから、かれこれ3年になる。亡くなったばかりの頃は、マチルダのことを思っては毎日のように涙し、週末には、ペットのチャリティ団体による電話カウンセリングサービスに電話をしては涙する日々だったが、時にいやされたのであろう、マチルダの死を憂い、悲しむ毎日は終わった。そして、マチルダに見守られながら奮闘して来た博士課程も無事修了し、晴れて社会学博士となった今、再びスタッフィーを飼うというのが、私の人生の次の目標となっている。もちろん、私の人生で最も苦しい時期を共にした、たった二人の運命共同体の一員だったマチルダは、これからも私の特別な犬であり続けることは言うまでもないが。Matilda, RIP(マチルダ、安らかに眠れ)。

Matilda, 22 May 2007 c Nobumi Kobayashi
注1:英国教会による祈祷書に「 灰は灰に、塵は塵に、土は土に」ということが記されている通り(https://www.churchofengland.org/prayer-worship/worship/book-of-common-prayer.aspx)、こちらではキリスト教の影響であろうが、生き物が亡くなったら、とにかく土に返して「自由」にしてあげるべきだという考えがあるので、亡くなったペットを火葬した後、思い出のある散歩道等にその灰をまいたりすることが多いようである。最近は、このような習慣をあまり気にしなくなっている傾向があり、遺骨(灰)を混ぜた入れ墨を入れたり (http://www.dailymail.co.uk/news/article-3433636/Ex-soldier-gets-tattoo-ashes-heroic-dog.html)、灰をクリスタルに合成し、指輪やペンダントにするサービスなどもある( https://ashesintoglass.co.uk/)。
注2:http://www.dignitypetcrem.co.uk/