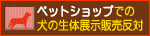映画「ユアン少年と小さな英雄」紹介
映画「ユアン少年と小さな英雄」紹介
スコットランドの人々の間で愛され続けている忠犬ボビー。19世紀に実在したテリア犬だ。主人の死後、14年間に渡ってその墓を守り続けたボビーのエピソードは代々に語り継がれ、スコットランドの首都エディンバラにはボビー像も建てられている。この有名な実話に当時の新聞に記されていた史実を加え、また魅力的な少年を架空の人物として配することで、大人も楽しめるハートウォーミングなドラマが誕生した。
映像は19世紀のスコットランドを見事に写し出している。英国の動物への愛護法が厚くなった経緯がかいましのばれる。
3月24日(土)、シャンテ シネ他にて全国順次ロードショー!
<ストーリー>
スコットランドのエディンバラ。貧困地区に母と暮らす少年ユアンは、警察官ジョン・グレイの忠誠なテリア犬ボビーと大の仲良し。ボビーは大きな雄牛を前にしても、決然たる視線でそれを立ち止まらせるほどの勇気を持っている。
る日、暴漢をとらえようとしたグレイは危機一髪となるが、そこへボビーが現れ、主人の身代わりに男が取り出したナイフに刺されてしまう。この事態を耳にしたユアンがグレイ宅へ駆けつけると、軽症を負ったボビーと病床に伏すグレイがいた。彼が病に侵され死期が近いことは、妻モーリンも承知のことだった。ユアンに偉人伝を渡し、この中のひとりのようになってほしいと、グレイは別れの言葉を残す。
それからまもなく、グレイの葬儀が執り行われた。深い悲しみに暮れるボビーは、主人の眠るグレイフライアー教会の墓地に忍び込み、そこで暮らすようになる。

その頃、町では登録犬制度が施行されはじめていた。ボビーの主人はすでに死んでいるために、法的にはボビーは野良犬扱いになる。ユアンの脱走に激怒していたジョンソンとスミシーは、ボビーを未登録犬として通報。最悪なことに、ボビーは捕獲され動物収容所に入れられてしまう。
<プロダクションノート>
スコットランドでもっとも有名な犬、「グレイフライアーズ・ボビー」
130年ほど前のスコットランドで実在した、ボビー。地元スコットランドはもちろん、ヨーロッパやアメリカでも多く人に愛され、教科書にも掲載されている有名な犬だ。ジョン・ヘンダーソン監督は、ディズニーによって1961年に映画化されたことのあるエレノア・アトキンソン原作のボビーではなく、新たな史実を盛り込んだボビーを作ることにこだわったという。「アメリカ人作家エレノア・アトキンソンが書いた本では、ジョン・グレイがスコットランドの農夫となっていますが、実際のボビーの飼い主は警官でした。また当時の新聞The Scotsmanの2つの記事から、市長がボビーを救ったことも確認しています。ユアン少年に関しては脚色ですが、他のキャラクターたちはすべて実在の人物にして、できるだけ実話に基づいた“古き良き時代”を描きたかったのです。」
愛らしい“ボビー”の名演技
この映画の成功のカギは、主演のボビーのキャスティングにあった。脚本が要求する演技をこなせることはもちろんのこと、ボビーのように誰からも愛されている歴史的にも有名な存在には、皆それぞれ固有のボビー像を描いているものだからだ。スカイ・テリア協会に聞けば「ボビーはスカイ・テリアだ」と言うし、ケアーン・テリア組合に問い合わせればケーン・テリアだと言うように。企画の段階から参加していたドッグ・トレーナーのジェリー・スコットは、映画に映ったときに一番適した犬種としてウエスト・ハイランド・テリアを選び、野性味を出すために毛を刈らずに伸ばし150年前の犬らしく見えるようにしたという。
彼がそのイメージに合う犬として探してきたのが、自分の飼い犬”ボビー“だった。彼は言う。「ボビーは僕の犬なんだ。2人の子供と妻、そしてボビーが僕の家族だ。彼はごく普通の家族犬として生きてきた。たまたまこの映画に出演したけれど今後も家族犬として生きてゆくよ。」
一度も演技をしたことのないペットとしての“ボビー”は、2年のトレーニングを積み、すばらしい演技を披露することになる。「我々の行ったトレーニング方法は犬よりもはるか上に立って教え込むといったものではなく、犬が自発的に考えることを重視したものなんだ。教室で子供たちを教えるのと同じで、何かを学んでいるという意識をしっかり持たせることが重要なんだよ。」だが、犬に教え込むことにも限度がある、とジェリーは語る。「クリストファー・リーのスピーチの間、ボビーがうなり声を上げてしまったのは想定外の出来事だった。何か気に入らないことがあったのだろうけど。その後、ドアの外側に猫が居たということが分かったんだ。それを阻止するような訓練までは出来ないよ」とジェリーは笑う。
(2007/2/25)(LIVING WITH DOGS)