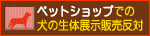小林信美の英国情報 (8)闘犬人気とピットブルの悲しい運命
闘犬人気とピットブルの悲しい運命
英国の「危険な犬」に関しては,この欄でも以前紹介したが(2004年12月2日発行)、ここ数年の間に状況はさらに悪化し、犬がらみの人身事件がマスコミで取りざたされるのは日常茶飯事となった。客観性を売り物にする天下のBBCまでもが、このところ頻繁に危険な犬関連の番組を報道しているところをみると、これは社会問題としてもかなり深刻なレベルに達していると言ってよいであろう。
社会学的にみるとマスコミの客観性というものはあってないようなものであるとみられているが(注1)、ここで英国のマスコミの姿勢に注目するのには、実はそれなりのわけがあるのだ。というのも英語圏のマスコミは記事になりそうなネタはどのようなものかを説明する際に「人が犬を噛む(Man bites dog−というような事件)」という表現を使う。これは、犬が人を噛むのは当たり前過ぎるが、人が犬を噛む事は珍しく記事にする価値があるからという論理から来ている。そういうわけで、このように犬が人を噛んだという事件がニュース記事として大きく扱われるということは、問題がかなり深刻であることを示すといえる。実際、ある統計によると過去4年の間に英国内で犬に襲われ救急病院に運ばれる人の件数は43%増したというから、マスコミがこれだけ騒ぎ立てる理由にもうなずける(注2)。
さて、前置きは長くなったが、今回、スポットライトを当てられているのは、1991年制定、1997年改正の「危険な犬に関する法律(Dangerous Dogs Act)で飼う事が禁止されているピットブル・テリア(正式にはアメリカン・ピットブル・テリア)だ。これは、一昨年の大晦日の夜にリヴァプールで5歳の幼女が叔父にあたる男性の飼っていたピットブル・テリアにかみ殺されたことが原因で、再び注目されるようになったものである。これに関しては、一緒に留守番をしていた45歳の祖母にあたる女性が麻薬とアルコールを乱用していたことから,事件は意外な展開を見せるのだが、何と言っても重要なのは幼女をかみ殺した犬が法律で禁止されているはずのピットブル・テリアであったことだろう(注3)。ここで注目すべきなのは、何故、この犬種がまだ国内にはびこっているのかということだが,合法的に繁殖するのは非常に困難なため、海外から密輸されているという以外にその理由は考えられない。果たして、ピットブルは何者によってどのような経路をたどり英国内に運び込まれているのだろうか?
そこで登場したのが、マスコミ界の優等生であるBBCである。実は、昨年8月、報道番組として非常に歴史の長い「パノラマ(Panorama)」の特捜班がこれまた違法である闘犬を地下活動で行っている組織を潜入取材し、闘犬とピットブルの密輸の実情をあばきだしたのである(注4)。これは、自称動物愛護支援者の記者が、北アイルランド州最大の闘犬団体に潜入し、その活動内容を克明に取材報道したもので、その結果警察の立ち入り捜査が入り、複数が逮捕されるという結果に至った。これによると、闘犬はほとんどの場合が賭博目的であるが、観戦スポーツとしての人気も非常に高いという。観戦スポーツと言えば聞こえは良いが、実際には参加する犬のどちらかが致命傷を追う、または死ぬまで戦わせる残酷なもので、敗戦した犬は、飼い主の手によって処分されるのである。
さて、肝心な密輸組織の実情だが、番組特捜班はある情報筋による内報からフィンランドでピットブルを繁殖するブリーダーを見つけ出し、ピットブルを購入したいという理由でそのブリーダーとの接触に成功する。番組中、屋外でくさりにつながれているピットブルが数頭、飼い主であるブリーダーを見て尾を振りながら飛びつき愛想を振りまいているシーンが映し出される。リング上では獰猛なこの犬種、人間、特に飼い主に対しては非常な愛情と忠誠心を示すのである。普通の家庭でペットとして可愛がられていたら、ごく普通の犬として平穏な暮らしをして行けたはずなのにと思うとブリーダーだけでなく、闘犬に拘る全ての人間に対し、激しい憎悪感が湧く。特に、動物愛護の観点から行くと、イギリスなどよりもはるかに意識の高いはずのスカンジナビアでこのようなことが起きるとは、人間とはほんとうに恐ろしい生き物だとつくづく考えさせられる。
話をまた密輸の話題に戻そう。ブリーダーからピットブルを一頭購入したBBC特捜班は、ここから一足、アイルランドへと飛ぶ。アイルランドでは、ピットブルは合法だが、法律上の手続きでは、ラブラドールとボクサーのクロスと表記され、何の問題もなくアイルランドに入国成功。その後、陸続きの北アイルランドまでは、取締まりのそれほど厳しくない国境を車で越えて行くこと数時間。ピットブルは難なく英国入国に成功する。
番組の意図は、違法であるピットブルの密輸がどれほど容易であるかという法の盲点をクローズアップすると同時に、闘犬がどれだけ残虐であるという点に焦点を当てている。そして、その残虐性というのは、闘犬に従事する人々の残虐性をそのまま映し出す鏡であると言って間違いない。番組の終わり近くに、闘犬団体の内部の信頼を得た潜入記者が、闘犬に参加するシーンを隠しカメラで撮った画面が映し出される。映像の質の悪さが、どこかの倉庫を利用して準備された暗いリングの様相を一層、不気味なものにさせ、残酷なものに全くダメな筆者は、闘犬のシーンには目を背けなければならないほどであった。しかし、聞くともなしに耳を傾けていた解説から、この対戦が血潮の飛びかう、非常に残酷なものであったことは確かである。
しかし、それよりもショッキングだったのは、勝負に負けた犬の処分の仕方である。リングで命を落とさなくとも、敗戦した犬は、通常、致命傷に近い重傷を負うため処分される。これは、闘犬は違法であり、違法のピットブルがかみ傷だらけで獣医に連れて行かれれば、闘犬の事実が外部に漏れるからである。今回の場合、対戦に敗れぐったりとしたピットブルは、参加者が賭博の掛け金を計算している合間に、リングの横にある簡易台所にそそくさと連れて行かれ、何事もなかったかのごとく電気ショックが与えられるのである。もちろん、この場面は映像に映し出されることはないが、音声から、一度で死にたえなかったらしく、再度、電気ショックを与えられ、その短い一生を終えるのである。その背景では、対戦の興奮からまだ覚めやらない参加者が今回の勝負の争点を声高らかに話し合っているのが聞こえている。そして、番組は静かに幕を閉じるのである。
先ほど、ピットブルは人間に対し通常、愛情深く、忠実であると書いたが、賭博と残虐性のスリルに溺れた飼い主の趣味のために闘犬として訓練させられ、命をはって戦う犬たちにこのような仕打ちを与えられる人間というのは、ほんとうに「生き物の片隅にもおけない」存在であるということを再度、確認してから、今回のコラムを終了したいと思う。
(注1) これはあまりにも単純な説明であるが、詳しくは:
Haralambos,M. and Holborn,M.,(2004) Sociology:Themes and Perspectives. London:Collins. 13章 Communication and the media を参照のこと。
(注2) 以下のリンクを参照のこと。http://www.inthenews.co.uk/news/crime/dog-attacks-up-by-43-over-last-four-years-claim-lib-dems-$1208088.htm
(注3) 事件の詳細については、以下を参照のこと。 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/merseyside/6222319.stm
実は、この事件が起きる直前の2006年12月30日にも北アイルランド州で散歩をしている子供と犬を連れた一家がピットブルに襲われるという事件があり、地方自治体は地区内で飼われているピットブル・テリアを押収し屠殺するという処分をとっていた。
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/6127688.stm
(注4) 番組の詳細は以下を参照のこと。番組のビデオも観られるが、非常に残酷なため愛犬家の皆様にはあまりお勧めできない。闘犬のシーンに関しては、実は筆者も勇気がなく観ていない。
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/6962563.stm