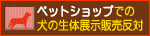小林信美の英国情報 (13)それでもロンドンが愛犬家天国でない理由 パート1
それでもロンドンが愛犬家天国でない理由 パート1
ロンドンで愛犬が猛犬に襲われたら?
– 増え続ける獰猛な「トロフィー・ドッグ」-
前回のこの欄では、筆者の久しぶりの帰国を機会に他の大都市と比べ、犬をオフリードで散歩させられる環境が整っているロンドンのよさを見直したことについて書いてみた。そういうわけで、ロンドンがいかにも愛犬家天国であるかのような印象を与えることになったかも知れないが、ロンドンにもロンドンなりの問題があることを忘れてはならない。そこで、この欄では今回から2回に渡って、ここ数年、焦点があてられている「危険な犬」と「犬の糞の処理」の問題が一般の愛犬家にどのような影響を与えているかについてご紹介したいと思う。
簡単に説明すると、まず「危険な犬」の問題は、いわゆる「危険な犬」に愛犬が襲われるということが一般の愛犬家にとっての一番の悩みの種であるということをお伝えしたい。さらにこれに関し、行政はほぼ何の措置もとっていない、というよりもとることができないという状況が問題を一層深刻化させていることをここで強調しなければならない。また、人間、特に子供がこのような犬に襲われることも多く、これにより、公共の場で犬をオフリードで散歩させることが近い将来禁止されることも考えられ、これにより一般の愛犬家が大きな打撃を受けることになるのは言うまでもない。
一方「犬の糞の処理」に関しては、ここ数年、民事問題が訴訟沙汰になることが多くなっており(*)、犬の糞の寄生虫が原因で特に子供が病気になった場合、自治体を相手取り訴訟を起こされることを想定し、自治体はその防止に力を注ぐようになってきていることがこの問題の重要点である。そして、これに対し、自治体の中には、飼い主に犬の糞の処理を徹底させるのは困難なので、犬を公園から閉め出すことで対処するという非常に極端な方法が2005年の新法の導入で可能になったことも同様に注目すべき点である。
いずれの問題も、他人を思いやることのできない少数の人間によって、一般市民が被害を被る結果になっているという点に注目していただきたい。たいていの場合、社会問題は少数者によって引き起こされ、そのコストを多数者が穴埋めすることによって、解決改善に導くのが当然といえば当然のことである。しかし、行政がこのような社会問題をコントロールできないのは、国家のあり方に問題があるように思われ、今のようなネオリベラリズムの原理で機能するイギリス国家の最大の問題であるとみられる。
さて、前置きが長くなったが、したがって、今回は以前にもこの欄でご紹介した「危険な犬」について再びスポットライトをあててみたいと思う(第六回目のコラムを参照のこと)。この時には、イギリスのある種の若い男性の間で「タフそうな」犬に人気が集まっているということに触れ、法律で危険な犬として禁止されているアメリカン・ピットブルテリアに似た、スタッフォードシャー・ブルテリア、またロットワイラー、秋田犬などの大型犬がこのような若者の手により「危険な犬」と化している実態を調査してみた。あれから数年たった今、問題はさらに深刻化したようで、拳銃や刃物等の代わりに武器となるよう、さまざまな犬と掛け合わせて獰猛そうな犬を繁殖するということがポピュラーになって来ているようだ。1991年制定の危険な犬に関する法律(*1)で危険な犬に指定されているアメリカン・ピットブルテリア、土佐犬、フィラ・ブラジリエロ、ドゴ・アルジェンテイーノなどの純血種を飼育していれば、議論の余地無く処分されることになっている。しかし、これらの純血種も闘犬のためにさまざまな犬を掛け合わせて創られたことを考えると、こうした犬種だけを禁止しても何の効果も無い事はこれで明らかである。そして、法の網の目をかいくぐり、このような違法な繁殖が横行しうる現状は、行政の盲点を鋭くつくと共に、武器代わりになるような獰猛な犬の飼育を法的に取り締まることは、今やほぼ不可能であるということを証明するようなものである。
こうして若者のタフなイメージを誇張するのに一役買っている「獰猛な犬」は今では非常に一般的になっており、マスコミにより「トロフィー・ドッグ」の名称で呼ばれるまでになっている。そして、トロフィー・ドッグは、比較的平和だといわれる筆者の住む北ロンドンの町でも以前よりも頻繁に見かけられるようになった。
夏になり天気のよいせいもあるが、数ヶ月ほど前からいつもの散歩道で見慣れない犬が散歩に来ているのによく気づくようになった。これは、前回のコラムでもご紹介したように、近所に新しい集合団地ができ新しい住人が引っ越してきたせいもあるかもしれないが、愛犬家にとっては実はあまり喜ばしいことではない。これは、なわばり意識から言っているのではない。問題は、ろくに訓練されていない獰猛な「トロフィー・ドッグ」でも遠くからみただけではそれとはすぐにわからないからである。もちろん、そのような犬に出くわしてから、獰猛な犬かどうかわかるまで数秒とはかからない。運が悪い場合は、愛犬が襲われ、獣医で応急処置を要するというようなこともある。そして、飼い主に治療費を請求したくとも、たいていの場合、そのような犬の飼い主は二度と同じ場所に現れないのである。
数週間ほどまえ、愛犬マチルダと散歩をしていると、毎夕、ラブの散歩に来るオシドリ夫婦のカップルが、うろたえた様子を見せながら、足早に私とマチルダの側を通り過ぎようとしていた。ちょっと様子がおかしいと思ったが、いつものように挨拶をすると、ご主人の方が立ち止まって「あれは、悪魔のような女だ」と遠くで2頭の大型犬に引きずられるようにして歩いている女性を指さした。奥さんの方はというと、涙で顔がぐしゃぐしゃになっていて、足下の愛犬のラブに目を移すと、背中が血だらけなのである。どうしたものかと事情を聞いてみると、さきほどの2頭の犬に出くわし、飼い主の素行がおかしいので愛犬をリードにつなぐと、その2頭のうちのジャーマン・シェパードのような外見をした犬が、突然、ラブののど元に食いかかって来たというのだ。そのカップルは、我が子のようにかわいがっているラブを救おうと後先を考えずに猛犬に体当たりで攻撃をやめさせようとしたため、二人共、その犬に噛まれたという。その間、ラブを襲った犬の飼い主は、おたおたするだけで何もできなかったというが、飼い犬が危険な犬であることはわかっていたようで「その犬(ラブ)殺されちゃう」と叫び続けていたという。ともかく、二人は愛犬を獣医に連れて行き治療をしてもらうということだったが、別れ際に「こんなことがあったこの公園にはもう2度と散歩に来ないから、お元気でね」と捨て台詞のように言って立ち去ったのだった。
また、最近では、近所の女性の飼うジャック・ラッセルが散歩に行く途中で、通りすがりのピットブルとマスティフを掛け合わせたような犬に、突然、襲いかかられるという事件があった。ここで恐ろしいのは、このピットブル/マスティフ系の犬は金属性のチェーンのリードにつながれていたもののあまりの勢いでひっぱったため、飼い主の若い男性もコントロールできなかったらしいのである。ジャック・ラッセルの飼い主の女性の話によると、彼女の愛犬はそれよりも数倍大きなピットブル/マスティフにのど元を食いつかれ、きゃんきゃんと悲痛な声で鳴きながらもがいていたのだが、ピットブル/マスティフは容易にはなそうとしない。そこで飼い主の男性がその鼻もとを力任せに殴りつけたが、顔面が血だらけになるほどに殴られても、口を開かなかったという。最終的に、その男性が犬の肛門に木の棒を乱暴に押し込んだため、驚いたピットブル/マスティフが口を開き、無事、ジャック・ラッセルは救出されたということだった。それでも、獣医の話によると、一歩間違っていたら気管が破裂し、ジャック・ラッセルは命を落としていたにちがいないという。それ以来、飼い主の女性は、散歩に出かけるのが非常に怖くなったといい、大型犬を見つけると逃げるようにしているということだ。
いずれの場合も、加害者にあたる犬の飼い主は犬をリードにつないでいたので、法的には「責任のある」犬の飼い方をしていたことになる。ところが、それでも自分の犬をコントロールすることができずに他の犬に被害を与えることとなったのは、法律に問題があると言わざるをえない。上記の例で触れなかったが、さらにここで問題なのは、被害者側の飼い主は、あまりのショックで加害者側の飼い主の住所氏名等を聞く事ができなかったことである。これは、法律上、持ち物と同様に扱われる犬が怪我をさせられ、獣医師による診療に費用がかかった場合は、被害を届けることができるのだが、加害者が誰か明らかでない場合はそれが不可能だからである(*2)。そして、届けを出した後でも、法廷で裁判が行われ、その措置が決められるということなので、どのような処分がくだされるかはケース・バイ・ケースであると認識しておいた方がよい。
ロンドンの警視庁にあたるメトロポリタンポリスによると、飼い犬が他の犬に襲われた場合、警察に通報しても、ほとんどの場合は何の措置もとらないという。これは、犬同士のけんかと扱われ、犬はそのような行動をとることが頻繁にあるからだという。ただ、その際、襲った犬が上記の通りの禁止された犬であることが明らかな場合や、その犬が非常に獰猛で危険であることが明らかな場合、また、人間が襲われた場合などには通報に応じることもあるという(*3)。しかし、これもケース・バイ・ケースであり、殺人事件などで警察官が総動員されている場合などは、飼い犬が襲われたぐらいでは、通報に応じられることはまずないであろう。テロ、麻薬問題などでロンドンでは警察官の需要が非常に高いため、窃盗など他の軽犯罪の場合でも同様の扱いを受ける場合があるため、これは仕方がないことだといわざるをえない。
そういうわけで、他の大都市に比べ犬をオフリードで散歩できるロンドンであるが、いつどこから獰猛な「トロフィー・ドッグ」が飛び出してくるかとびくびくしながら歩かなければならなくなった今、犬の散歩はそれほど楽しいことではなくなりつつあるのだ。
(*) これについては、ネオリベラリズムの台頭で社会のあり方が変化したということに起因していると思われるが、その説明は紙面の都合で割愛させていただく。
(*1) 危険な犬に関する法律については以下のサイトを参照のこと。
http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1991/Ukpga_19910065_en_1.htm
(*2) 上記のセクション3を参照のこと。
(*3) メトロポリタンの職員との電話インタビューによる。危険な犬への対応に関する詳細は以下のサイトを参照のこと。http://www.met.police.uk/