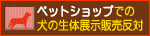動物孤児院 (105)愛犬を安楽死させる、ということ
動物孤児院 (105)愛犬を安楽死させる、ということ
老犬介護の日々
一ヶ月前、私たちは愛する犬に安楽死を選択しました。
飼い主“ママ”と私たち夫婦は、「仕事に行っているあいだ愛犬を預かってくれる人を探しています」のポスターを通して知り合いました。週に5日、朝7時から夕方5時までと、それに飼い主ママが数週間に渡る休暇や出張に出るときはその間、私たちが世話をすることにしたのです。15年も前のことです。
近所の人たちは犬は私たちが飼っていると思っていたようです。一日の半分以上は私たちのもとにいるのですから、当然ながらすぐに情がわき、我が家の犬同然でした。夫は、犬や猫が好きでない両親のもとで育ち、犬に興味がなかったのに、この犬がうちに来るようになってから、犬のすばらしさに目覚めたようです。その犬はいつも、なぜか一番構おうとしない夫の足元にすりよっていき、離れようとしませんでした。
 安楽死させるのが一般的
安楽死させるのが一般的
あと四ヶ月で19歳でした。数ヶ月前から後ろ足が急激に衰え、立ち上がるのに時間がかかるようになっただけでなく、耳も遠くなり、目もおそらくあまり見えていないか、見えても認知症に関係あるのか、物にぶつかるようになり、失禁も徘徊も始まりました。それでも何とか歩いて水飲み場まで歩けたし、肉を鼻先に持っていってやれば食べることができたので、物が食べられる間はこれでいい、介護を続けていこうという気持ちでした。
犬を犬用バギーに乗せて歩いていると、珍しがられ、いろんな人から話しかけられ、会話がはずみます。ドイツでは老犬をバギーに乗せて歩く光景はほとんど見られません。“歩けないほどの高齢になれば安楽死”がドイツ流なのだと思います。ここでは、周囲(知人と近所)の犬の最期はほぼ100%安楽死でした。私は全く知らない通りがかりの人から、「安楽死させたほうがいいのではないのですか」と言われたことが三度あります。帰宅してから夫に言うと、「じゃあ、あなたの母親が年をとって認知症になったら安楽死を選びますか、と言い返せばよかったのに」と憤慨しました。(実際、ドイツでは最近、人間の安楽死についての合法化の話題として取り上げられています。)
ドイツ人は、ペットが不治の病で苦痛を伴い、助かる見込みはないという場合や、高齢で歩けなくなった、自ら食べることができなくなった、という段階に達したときに、苦しみから解放させるという意味で、安楽死を選びます。(飼えなくなったからというような、飼い主の都合で安楽死をさせることは法律で禁止されています)。
飼い主ママは、半年ほど前から安楽死を口にするようになっていたのですが、私たち夫婦は、「まだ早すぎる」と反対しました。彼女も周囲から色々言われたこともあって、「寝たきりの状態では犬にとって残酷なだけではないか」と思っていたのです。それは私たちも十分に理解できました。しかし、私には彼女が愛犬を抱っこしているとき犬の目が明らかに輝きを増すのを見て、寝たきりでもいい、クッションをオシッコで濡らしてもいい、あるがままを受け入れることができたのです。
そこで私たち三人は取り決めをしました。
食べなくなったら、介助しても立ち上がれなくなったら、水を飲まなくなったら……その時が来た、送り出す時が来た、とする。
そうこうしているうちに、安楽死という提案がしばらく消える事件が起きました。飼い主ママが突然、頚椎の手術をすることになったのです。退院しても、エレベーターのないマンションの三階に住む彼女には10キロの犬を抱えて階段を昇り降りすることなど到底無理でした。私たちは彼女が退院した後も犬をうちで預かることにしました。彼女のドイツ人の友達は口をそろえて、「犬は安楽死させたら?」と勧めましたが、今度は彼女のほうが、「自分の入院のせいで、つまり、人間の都合で、愛犬を安楽死させることはできない」と言い切ったのです。
いつ安楽死を?安楽死の選択、犬のためにいつがベストなのか、の葛藤に悩みました。
そして、虹の橋へ
 ある日、食べ物にも水にも見向きしなくなりました。介助して立ち上がらせても倒れる。送り出すときが来たのです。
ある日、食べ物にも水にも見向きしなくなりました。介助して立ち上がらせても倒れる。送り出すときが来たのです。
飼い主ママは2時間のあいだ、ソファで「マイ オールド ベイビー、愛してるわ、私の最愛の犬」と言いながら犬を抱きしめていました。それからかかりつけの獣医先生に電話を。天国に送り出すときは薬の匂いのする、犬たちの大っ嫌いな診察室ではなく、自分の匂いや大好きな家族の匂いに囲まれた環境がいいのです。
穏やかでやさしい、のっぽの獣医先生は夜遅かったのに、すぐに駆けつけてくれ、犬を見るなり、「ああ」と低くうなりました。実は獣医先生も半年前ぐらいから、「そろそろ安楽死のことを考えてもいいのでは」と言っていたのです。飼い主に抱っこされたこの超高齢犬は、獣医先生の目には、「もっと早く安楽死させてもよかった状態だ」と映ったようでした。
しかし、私たちはあの晩こそが、「早すぎず、遅すぎない、ベストな時だった」と今でも信じています。
安らかな死でした。最期の息の後、飼い主はもちろんのこと、夫は「ぼくはティミーを本当に愛していた」と泣きじゃくりました。両親が亡くなったときはほんの少し涙を流しただけだった彼ですが。
飼い主と私は前にペット墓地の下見をしていたので、そこに埋葬するつもりでいたのですが、「お宅には庭があるのだから庭に埋めたらいいですよ」と言う獣医先生の言葉に夫はシャベルを持ち出し、穴を掘り始めました。言われた通り、穴は70センチの深さに。飼い主は花屋から花輪と冬でも可憐な白い花をつけるクリスマスローズを買って来ました。お墓に毎晩ろうそくを点すとき、私のすぐ横に犬の魂が来ている、と思えます。
もうしばらくしたら墓石を置くつもりなのですが、刻む言葉を考えています。「永遠に愛します。また会う日まで!」が私の案です。それ以外に言葉が見つからないのです。
Until one has loved an animal, a part of one’s soul remains unawakened.
– Anatole France
「動物を愛する」という体験をするまで、その人の魂は未完成のままである。
アナトール・フランス (19世紀のフランスの作家)