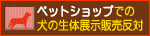小林信美の英国情報(25)動物愛護先進国、英国と「後進国(?)」日本
先日、在英日本大使館から、来る9月1日に大使館前で行われる反イルカ漁団体による大規模なデモに関する警告メールが送られて来た。このメールは、在英日本人に注意を促すことを目的としたものであり、デモに対する日本政府の見解については、何ら明らかにされてはいない。
ほ乳類で、しかも知能の高いイルカを残酷な方法で殺傷することは、倫理的に許されない行為であると多くの日本人が感じていることくらい公表してくれてもよさそうなものだが、日本政府は、これを「古来の文化」であり、保護すべきであるというような姿勢を外面的に保つことが、少しいい方は古いが「NOと言える日本」を海外にアピールするのに最適な政策とみているようだ。
これは、ここ英国で、残酷な狐狩りが(貴族階級によってであるが)古くから行われてきた英国の伝統であり、将来、受け継がれて行かなければならない行事であると主張する保守党の政策に似ているように思われる。
しかし「ああ言えばこう言う」式の議論に長けている英国の政治家には、狐を害獣であると議論できる逃げ道があるのに対し、イルカを害獣と議論し駆除を正当化させ、国際世論を納得させるのは、ほぼ不可能であり、そういう意味で、イルカ・クジラ漁に関する日本の外交政策は、日本政府の「英米流」PRスキルの欠如を顕著に表すものであると言える。
しかしながら、第二次世界大戦後の国際社会の土台は、英米文化(*1)により培われた倫理観に従い成り立っていることから来ており、このことは、日本政府の欠陥とは言えないということをここで付け加えておきたい。これをさらに詳しく説明すると、国際社会における倫理的問題に関しては、英米文化の根底にあるキリスト教の考え方により、物事の善悪が決められており、それ以外の考え方を一般化するのは非常に難しいということがその背景にある。そして、一般的に万国共通と考えられている動物愛護というコンセプトも、実は、英米の倫理観にかなり影響を受けているものであるということは、忘れてはならない。
前置きは長くなったが、今回は、動物愛護のテーマに焦点を当て、英国から愛犬情報を発する立場の人間として、巷で広く「信仰」されている「英国は、動物愛護先進国である」、また日本は「後進国である」という考え方について探ってみたい。
ここでまず、動物愛護という考え方は、それぞれの文化に特有の倫理観に従い培われていくものであり、その定義は、国ごとによって違うはずであるということを提言したい。
これは、英国では狐狩りをしているから、イルカやクジラを殺してもよいということを言っているのではなく、異文化間での倫理観に関する問題を比較するということは、非常に複雑であり、それを試みようとすること事態に無理があるということを指摘したいのである。
例えば、キリスト教では「生け贄」の考え方があるのに対し、仏教ではそのような考え方がないということに焦点を当てると(注1)、キリスト教文化圏である欧米の方が動物愛護に関し「進んでいる」というのは、どのようなことなのかという疑問が出て来る。そういうわけで、単純にみると、これは考え方の善し悪しではなく、その違いが問題となるので、単純な比較はできないということになるのだ。
もちろん、動物愛護というコンセプトに当てはまる、さまざまな行動を量的に比較することは可能である。例えば、英国と日本での犬の殺処分の状況を比較するにあたり、まず手始めに「英国内の犬の殺処分」をインターネットで検索してみると、かなり以前から「社会問題」として注目されていたことは、一目瞭然である。ちなみに、大衆紙メトロの報道によれば、2016年に英国で殺処分された犬の頭数は、2万頭にのぼるという(注2)。さらに同紙によると、このコラムでも以前紹介したことのある、英国の動物愛護のシンボルともいえる「バタシー・ドッグス・アンド・キャッツ・ホーム」でも、収容する犬の25%が殺処分されているとされている。
一方、日本の環境省の報告によると、平成27年(2015年)に日本で殺処分にされた犬の頭数は、英国を下回る15,811頭にまで減少しているというのだから(注2)、公表されている野良犬や捨て犬の殺処分数に関してだけ言えば、英国が動物愛護先進国であるという肩書きは、通用しないということになる。
それでは、日本が動物愛護に関して後進国であるということは、どういうことなのだろうか。上記で議論したように、動物愛護というコンセプトも、英米の倫理観に従い定義されていることから、当然、日本の倫理観はそれと比較し、劣っていると考えられることになる。しかし、この見方に従うと、日本が動物愛護に関して後進国であるといわれる理由は、その水準がどうであるということよりも、英米と違うということが問題となることがわかる。
そういうわけなので、英国の動物愛護の方が日本よりも進んでいるという考え方が、なぜ、どのようにして受け入れられて行ったのかというプロセスを理解することが重要になろう。そして、それをするには、 日本社会の政治的、経済的、文化的な状況などに焦点をあて、関連事象を歴史的にヒモといて行くということが必要であり、一朝一夕に解決できる問題ではないということがわかる。
ローマは一日にしてならずということわざがあるが、社会現象としてのいわゆる固定観念というものも、きちんと形成されるまで、同様にかなりの時間を要する。そして、時と共に変化するさまざまな偶発的要因に影響を及ぼされ、ある一定の観念が多くの人に「真実」であると受け入れられるようになるのである。ここで偶発的要因という言葉を使ったが、固定観念をコントロールすることは非常に難しい。しかし、マルクス主義で有名な、カール・マルクスの説にある通り、支配階層による考えが広く支持される傾向にあるというのは、否定できない「現実」であるように思われる。例えば、国際メディアを牛耳る、公共放送のBBCなど、英国メディアの報道に関する方針は、英国のいわゆる支配階層にあたる人材の視点に大きく左右される傾向にあり(注4)、国際世論に英国支配階層の見解が反映されやすいということをここで指摘しておきたい。これらの点を考慮に入れたうえで、日英愛犬愛護の観念の違いに影響を及ぼしたであろう要因を探してみると、英国で1950年代に設立されたJapan Animal Welfare Society(ジャパン・アニマル・ウェルフェア・ソサエティ)に行き当たる。
この団体は、戦後間もなくの東京に駐在していた当時教師であったエレナ・クロース女史と、その友人のローナ・ガスコイン侯爵夫人の二人の英国人女性が、動物実験に使われていた野良犬の残虐な扱いに心を痛め、英国に帰国してすぐに立ちあげられたものだという(注5)。
クロース女史の詳細は明らかではないが、北イングランド出身の侯爵夫人の友人であるということは、貴族階層の人間と社交する機会のある社会的地位の高い者だと考えられる。ここで重要な点は、当時戦勝国であった英国の恵まれた人間が、敗戦国で、倫理観の違う日本国民の行動を改めるためにチャリティ団体を設立したということを当然のように受け止めてよいのであろうかということだ。当時の日本は、太平洋戦争に負けたがために、民主化などを含め、アメリカの指示に従い、国のさまざまな制度の「西洋(アメリカ)化」をすさまじい勢いで行っていた。そうした環境の中、同様に戦勝国であった英国の国民の指示で、動物愛護に関する指導を受けるというのは、決して不自然なことではなかったに違いない。
欧州と英国の高校、大学、大学院で教育を受け、英国滞在が約30年になる筆者には、同団体の掲げている動物愛護に対する考え方は、ほぼ当たり前のことのようにみられる。ただ、非西洋国である日本の動物愛護に対する意識の低さに憂慮し「英国のような先進国(西洋)に見習う必要がある」という差別意識ともみえる設立者の態度を、疑問も持たずに受け入れるのはどうだろうか。
ここでポイントとなるのは、英国や西洋は正しく、非西洋の日本は野蛮で間違っているという考え方である。例えば、戦前の英国(1937年)でも、空襲の混乱を予想した行政の奨励により、75万頭ほどの飼い犬が殺処分を受けたということが最近の報道でわかっており(注7)動物愛護の先進国である英国でも、戦時中の混乱期には、犬の愛護にそれほど力を注ぐ事ができていなかったことが伺われる。そして、上記団体の設立者はもしかしたら、英国内のこのような状況について、全く無知だったということも十分考えられる。公式の資料ではないのだが「帝国の犬たち」(注6)という個人のブログによれば、 日本は、西洋の影響を受けてか、明治維新から犬の愛護に関してさまざまな努力がなされていたことがわかる。もちろん、心ない人もおり、虐待などもかなりあったようだが、このコラムでも取り上げて来ている通り、現代の英国にもそのような例は多々あることから、それはどこの社会にもあると考えて間違いない。
ちなみに、ジャパン・アニマル・ウェルフェア・ソサエティは、現在もなお、日本の状況が他の先進国より「遅れている」ということを憂い、慈善事業を続けていると最近の日本のジャパン・タイムズで報道されている(注7)。もちろん、日本では、まだまだ生体販売が横行し、子犬が商品のように扱われているような問題も深刻である。
ただ、以前にもこの欄で紹介したように、こちら英国でも闘犬やオンラインでの犬の販売等、犬の愛護に関し、さまざまな問題を抱えているのが実情である。特に、最近の英国では、ジャーナリスト等、オピニオン・リーダーが社会の底辺層の事情を把握していないということが指摘され、問題となっている(注9)。そして、こうした、いわゆるエリート階層の人間が政治やマスコミを動かすこの国では、新聞などで「世論」といわれるような考え方も、実際には現実とかなりかけ離れた「理想論」であることもかなりあるのである。
そういうわけで、ここで提案したいのは、盲目的に英国などの西洋諸国のやり方が正しいと思い込まず、日本の倫理観にあった動物愛護に対する考え方を築き上げて行く事が必要なのではないだろうかということだが、どうだろうか。
(*1)これは、英国が産業革命と帝国主義で英語文化を世界中に広め、その後、国力が衰えてきた19世紀後半くらいから、アメリカ合衆国の台頭により、形成された世界システムの影響であると言える。以下の文献は、参考になる。
Kristin Haugevik, From British Empire to Anglo-American Hegemony, British Politics Review, Vol. 3-2.
(注1)Animal Welfare in Different Human Cultures, Traditions and Religious FaithsE. Szűcs,* R. Geers,1 T. Jezierski,2 E. N. Sossidou,3 and D. M. Broom4
Asian-Australas J Anim Sci. 2012 Nov; 25(11): 1499–1506.
(注2)http://metro.co.uk/2016/01/09/battersea-dogs-home-puts-down-almost-a-quarter-of-its-dogs-every-year-5611931/
(注3)https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html
(注4)https://www.theguardian.com/education/2017/feb/23/ppe-oxford-university-degree-that-rules-britain
(注5)http://jawsuk.org.uk/our_story/
(注6)https://ameblo.jp/wa500/theme1-10021482731.html#main
(注7)http://www.bbc.co.uk/news/magazine-24478532
(注8)https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/25/national/british-charity-jaws-still-raising-money-awareness-animal-welfare-japan-long-wwii/#.WaLq-YVjtFU
(注9)https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/23/grenfell-british-media-divide