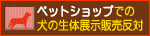小林信美の英国情報 (3)断尾と断耳はほんとうに必要なのか?
(3) 断尾と断耳はほんとうに必要なのか?
先日、小春日和のリージェンツ・パークを散歩していたら、断尾されていないヨークシャーテリアを見かけた。体の割に大きめの尾だったが、全く違和感はなく、魔法使いのほうきのような尾で舵をとるように懸命に歩く姿が愛らしくも見えた。しばらく前まで目にも止めなかったであろうこの光景だが、最近の雑誌取材で断尾に関して専門家に話を聞く機会を持ってから、断尾されている犬種に自然と目が行くようになった。
さて、断尾に反対する英国内の団体「アンチ・ドッキング・アライアンス(Anti Docking Alliance-断尾反対連盟)によれば、イギリスで従来、断尾されている犬種はヨークシャーテリアのほか、52犬種と非常に多い。2000年に結成されたばかりの同連盟は、断尾に反対する理由として断尾賛成派は, けがをしやすくなるなどもっともらしい理由を掲げているが、大抵の場合が「犬の容姿を保つための、いわゆる美容形成的なものであること」から不必要であり、残酷であることを挙げている。
一方、断尾継続を訴える、これもまた英国内の団体「カウンシル・オブ・ドックド・ブリード(Council of Docked Breeds – 断尾されている犬種のための評議会)によれば、第一に不必要なけがを防ぐため、第二に衛生上の理由、そして第三にブリードスタンダードを守るためとしている。ここで、各項目についてさらに詳しく見てみよう。まず、第一番目のけがに関するもの。猟犬の尾はイバラなどに絡まってけがをすることが多い。ネズミ捕りや、小動物の狩に使われていたテリアも、尾は狩のじゃまになるからとしている。さらに、使役犬でなくとも、尾を必要以上に振ってけがをするペットは非常に多いという。第二の衛生上の理由としては、ヨークシャーテリアなどの長毛種は、糞がついて不潔になりやすいからという。実は、農家で羊の尾を断尾する理由もこれと同じ理由からである。さらに、第三の理由のブリードスタンダードでは、従来、断尾されている犬は、尾の長さ、形などにこだわらずスタンダードが設定されているため、尾の美しさに関して疑問な点が多いと考えられる。断尾が禁止された場合、尾の形を考慮するばかりに交配に使用できる犬の数が激減する恐れがあり、そのため、遺伝性疾患が増える可能性が高いとしている。
動物愛護先進国として知られているイギリスだが、少なくとも断尾に関しては、大陸ヨーロッパに先を越されていると言っても過言ではない。断尾禁止を呼びかけた唯一の国際条約に、欧州評議会の西ヨーロッパ諸国諮問機関によって1987年に提案された欧州内行政指導があるが、イギリスはこれに調印していないこともそのよい例と言えよう。しかし、1991年英獣医師法の改正にともない、1993年7月1日より獣医師以外による断尾は禁止されることとなり、イギリスは断尾禁止へ一歩近づいた形となった。さらに、政府の動きを受け、カウンシル・オブ・ロイヤル・カレッジ・オブ・ヴェテリナリー・サージェオン(Council of Royal College of Veterinary Surgeons-王立獣医科大学評議会)は、1992年11月、「健康上、及び、病気予防以外の理由による断尾は倫理にかなっていない」と定めた。さらに病気予防の詳細にはさまざまな条件がつけられており、断尾はそう簡単には行えないとカウンシル・オブ・ドックド・ブリードは付け加えている。
さて、それほどまでに断尾を行うのが困難なはずのイギリスであるが、私は、まだ、断尾されていないボクサーもロットワイラーも見たことがない。知り合いでジャイアント・シュナウザーを飼っている女性も、国内ありとあらゆるところを探したが、断尾されていない子犬は1頭も見つからず、仕方なく、断尾済みのシュナウザーを飼うことにしたとも聞いている。どうやら、この国のブリーダーの多くは、法律違反を承知で自ら断尾をしているようなのだ。断尾といえば、大手術を想像するが、何のことはない、生後3日〜5日のまだ目の開かないうちの子犬の尾に輪ゴムを巻いておけば、血液が流れないので尾は数日すると自然に落ちるというのだ。長年、繁殖を手がけているブリーダーならば、断尾はそれほど難しくないというわけだ。もちろん、獣医師によれば、輪ゴムによる断尾は化膿したり、大事に至る恐れがあるので、できるだけ避ける方がよいと忠告するが、これは残念ながら馬の耳に念仏となる。前述の通り、伝統的に断尾されている犬は、未だに断尾され続けているのだ。
ところが、断耳となると話は違う。私個人の経験から言えば、とにかく、どこを見渡しても断耳された犬は見つからない。ちなみに日本では立ち耳でおなじみのドーベルマンとボクサーの英ケンネルクラブによるブリードスタンダードを調べてみると、ドーベルマンは、基本的には垂れ耳となっているが、立ち耳でも可とされている一方、ボクサーは立ち耳に関してはひと言も触れられていない。それでも、一般的に、愛犬家は断尾に賛成していても、断耳は残酷だという認識を持っているようで、断尾されているボクサーでも必ず耳は垂れているのが普通なのだ。これは、なぜなのだろうか?アンチ・ドッキング・アライアンスの会報の2000年9月・10月号によると、これには王室の見解が多大に影響していたというのだ。これによると、19世紀後半に、当時のプリンス・オブ・ウェールズ、後のエドワード7世が断耳は残酷だと訴えたことから、英ケンネルクラブが断耳を禁止し、それ以来、断耳は残酷だとみなされるようになったのである。そういうわけで、この「断耳禁止令」は綱吉の生類憐みの令と同様、非常に主観的なものであったということだ。
断尾・断耳に関する問題は、最終的には倫理的なものである。しかし、これらの行為は、人の目に触れないところで生後3〜5日の末梢神経の発達していない子犬に行われているため、どの程度、残酷なのかを議論するのは非常に難しい。前述の通り、農家では非衛生的(糞がついて、ウジがわくので)だということで、子羊を必ず断尾するが、これを残酷だという動物愛護団体は今のところないようだ。ところが、これが食用にならない馬となると、断尾は禁止なのである。さらに、家族の一員であるペットとなれば、倫理観の基準も当然、変わるはずである。
個人的な意見としては、自然にあるべき姿を人間の手で変える必要はないと思う。それが生存に悪影響を及ぼすのであれば、進化の段階でなくなっていたはずであるからだ。我が家のテリアも興奮しやすいタイプなので、いつも尾をモーレツに振りまくっている。向こう見ずな性格で、散歩に行けば、リスや狐を追いかけて、イバラのある草むらなど全く気にせずに飛び込んで行っては、いつも傷だらけになって帰ってくる。これまで、何度も足の裏を切ったり、腿に大きなあざをつけて獣医さんの世話にならなければならないことも何度もあったが、一度も尾にけがをしたことはない。もしかしたら、我が家の愛犬はラッキーなのかしら。
(2004/04/03)
(ライター・小林信美 ![]() Matilda the little Staffie!)
Matilda the little Staffie!)